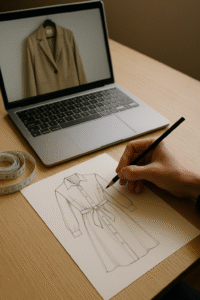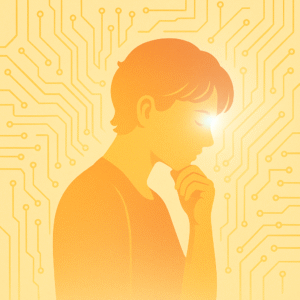売上の基本は「単価×個数」。
いまの日本は単価だけが上がり、個数(消費・生産)は減っている。
企業の利益はコスト増に圧迫され、特に中小企業は限界に近い。
それでも政治は「賃上げ」を叫び、メディアは今さら「為替」を騒ぎ始めた。
この国の“数字の景気”の裏で、現場はどうなっているのか。
売上の基本に戻って考える
企業の売上は「単価×個数」で決まる。
この式を日本全体に当てはめると、今の日本は「単価だけ上がり、個数が減っている国」だ。
物価は上がり続け、円安と人件費高でコストは膨らむ。
一方で人口減と消費の冷え込みで、物やサービスの“量”は減少。
つまり、見かけの売上は増えても、実質的な利益は減っている。
「単価上昇 → 賃上げ」は順序が逆
本来、賃上げは利益の結果である。
生産性が上がる → 利益が増える → 給料が上がる
という順序が正常だ。
しかし今は逆だ。
物価が上がる → 生活が苦しくなる → 給料を上げざるを得ない
中小企業にとってこれは耐えがたい構図だ。
輸出で儲かる大企業は円安の恩恵を受けるが、
中小企業は仕入が輸入依存で、円安が直撃する。
同じ「日本企業」でも、まったく別の国を生きている。
利益が出にくい構造になっている
利益は「売上−コスト」。
ところが、原材料・エネルギー・物流・人件費のすべてが上昇中。
売上は価格転嫁でかろうじて支えられているが、個数が減っているため利益は増えない。
中小企業の多くは、利益ゼロで延命しているに過ぎない。
なぜ政治家は「物価上昇」に警鐘を鳴らさないのか
それは、「インフレ=景気回復」と信じ込んでいる(あるいは装っている)からだ。
物価が上がれば名目GDPが上がり、統計上は“成長しているように見える”。
しかし、現実の国民生活は逆だ。
物価上昇は消費を冷やし、中小企業を削り取る。
それでも政治家は「賃上げで乗り切ろう」と言う。
なぜなら、それが数字を良く見せる唯一の手段だからだ。
メディアが今さら為替を騒ぐ理由
マスメディアが急に「為替対策」と言い始めたのは、問題が“体感”として広がったからだ。
光熱費、食料、ガソリン、家賃——
生活のあらゆる部分で円安の影響が見え始め、ようやく国民が怒り始めた。
それまでは「スポンサーに都合が悪い話」は報じなかっただけだ。
結論:単価でつないで、利益を削る経済
今の日本の構造を整理すると、こうなる。
| 要素 | 現状 |
|---|---|
| 単価(価格) | 外的要因で上昇 |
| 個数(消費・生産) | 減少傾向 |
| コスト | 全面上昇 |
| 利益 | 縮小・ゼロに近い |
これが“見かけ上の好景気”の正体だ。
賃上げよりも前に、なぜコストを上げざるを得なくなったのかを問うべきだ。
数字ではなく、現場が息をできる経済を取り戻す必要がある。
本当に必要なのは「数字をよく見せる政策」ではない
政府がやるべきは、賃上げよりも中小のコスト軽減策と為替の安定化。
物価が上がり続ける構造に手を打たない限り、賃上げは単なる数字合わせに過ぎない。
生産と消費のバランスを整える政策、地域や中小が“利益を残せる”仕組みをつくることこそが本筋だ。
そして私たち現場も、国の数字に合わせるのではなく、自分たちの利益構造を守る視点を取り戻さなければならない。
価格転嫁を恐れず、固定費を見直し、小さくても利益を確保できる経営体質に戻すこと。
それが、静かに崩れていく日本の中で生き残るための唯一の現実解だと思う。