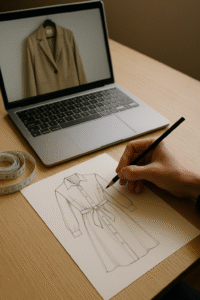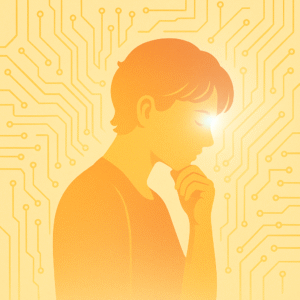「売れる商品がいい商品」。
この言葉は、僕がアパレルの世界に入ってから何度も耳にしてきました。
若い頃は少し味気なく聞こえたものです。
でも、30年以上この仕事を続けるうちに、今ははっきり思います。
やっぱり売れる商品こそ、いい商品だと。
そして、それを支えるのは“いいものを作る力”と“売る力”──その両輪だと感じています。
本文
■1.「いいものを作れば売れる」と信じられていた時代
30年以上前、僕が業界に入った頃は、
「いいものを作れば自然に売れる」という考え方が主流でした。
素材、縫製、シルエット──丁寧に作れば必ず結果がついてくる。
そんな空気がまだ残っていた時代です。
でも僕は、当時から少し懐疑的でした。
どんなに丁寧に作っても、倉庫に眠ってしまえば意味がない。
服は人に着られてこそ、初めて“商品”になる。
作り手の理屈ではなく、着る人の気持ちこそがすべて。
その感覚だけは、今も変わりません。
■2.ユニクロが変えた「良いものの定義」
やがてユニクロが現れ、業界の常識は大きく変わりました。
彼らが示したのは、
「良いもの」だけでは売れない。
「良い仕組み」で届けた人が勝つ。
品質とは、高価な素材や複雑なデザインではなく、
「誰でも手に入れられる安心感」へと変わった。
ユニクロは“良さ”を再設計し、
“伝わる力”を商品価値に変えたんです。
この流れを見て、僕は確信しました。
いい商品とは、売れる構造を持った商品。
つまり、“売れる”ということ自体が品質の一部なんだと。
■3.過去のやり方を続けるアパレルの苦境
今も、昔のままのやり方で苦しんでいるアパレルは少なくありません。
真面目に作り続けているのに、売れない。
展示会に頼り、情報発信も遅れ、
お客様との接点がどんどん減っていく。
それは“モノが悪い”のではなく、
「売る努力」を怠っているだけなんです。
今の時代は、
つくる努力と同じくらい、伝える努力が必要です。
SNSや動画での発信、見せ方、届け方──
そこまで含めて“モノづくり”なんだと思います。
■4.「残す」より「届く」ことを大切に
ファッションは衣食住の中で、唯一“なくても生きられる”もの。
けれど、人の心を動かし、
その日の気分を少し明るくしてくれる力がある。
だから僕は、
モノとして残すことにこだわるより、
人に届くことの方が大切だと思っています。
倉庫に眠るより、
誰かのクローゼットで擦り切れるまで着られる方がずっといい。
モノは残らなくても、
その服を着た人の記憶や気持ちは、ちゃんと残るからです。
■5.結論 ― 売れる商品がいい商品
今の僕にとって、“売れる”とは「人に必要とされている」ということ。
誰かの生活の中に入り、
作り手の想いがきちんと届いているということ。
だから、やっぱり思います。
売れる商品が、いい商品。
それは、単なる商売の話ではありません。
“つくる努力”と“売る努力”の両方がかみ合った結果。
どちらかが欠けても、長くは続かない。
ファッションは、誰かに着られて完成する仕事。
だから僕はこれからも、
売れる商品を、誇りを持って作りたい。