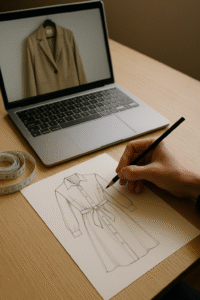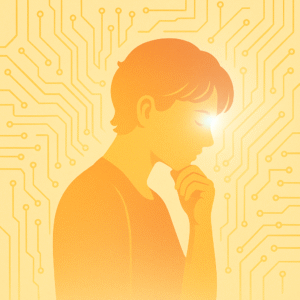友人との何気ないディスカッションで、こんな話題になった。
「欧米の若者も、日本の若者も同じなのか?」
「成熟って、もしかして退化と同じなのかもしれない。」
「刺激や新しい物を追い求めることをやめた時、人は老いる。」
この問いは一見、世代論に聞こえる。
しかし実は、人間の根源的な生き方の問題なのかもしれない。
欧米のZ世代にも見える“早すぎる倦怠”
スマホを片手に生まれ、SNSで育ち、AIと共に成長したZ世代。
アメリカでもヨーロッパでも、彼らは共通してこう語る。
“We’re too young to be this tired.”
(こんなに疲れてるのに、まだ若すぎるよな。)
彼らは世界の複雑さを、10代で既に理解してしまった。
政治も環境も経済も、何が起きているかを“知っている”。
けれど、その知識は行動の熱を奪い、
「わかっているのに動けない」という早すぎる成熟=倦怠を生んでいる。
成熟とは、刺激を求めなくなることではなく、驚かなくなること
成熟の本質は「落ち着く」ことではない。
むしろ、驚くことをやめてしまう瞬間にこそ、老いが始まる。
- 若さとは、未知を楽しむ筋肉。
- 成熟とは、未知を避ける理性。
理性が過剰になると、世界は“理解済みの風景”に変わる。
そして、人は安全の中で、ゆっくりと感受性を鈍らせていく。
「飽きた社会」――刺激が飽和したあとに残るもの
20世紀は「新しさ」に価値があり、
21世紀は「快適さ」と「効率」が支配した。
情報も商品も過剰に供給され、
“もうこれ以上の驚きはない”という飽和点に達した社会では、
人間は「飽き」によって老いる。
成熟とは、文明が「驚かない仕組み」を完成させてしまった状態でもある。
合理化・最適化・自動化――それらは便利さと引き換えに、
人間の“感じる余白”を削っていった。
「退化としての合理化」――感情を使わない社会の危うさ
現代社会の成熟は、実は「退化の洗練」かもしれない。
- 争わない
- 無理をしない
- 感情を抑える
- 効率的にこなす
一見穏やかで理性的に見えるが、
それは熱のない生でもある。
人間は本来、非合理で、感情的で、矛盾に満ちた存在だ。
その“揺れ”の中にこそ、生の実感が宿る。
しかし今や、私たちはAI的な“最適化された生”に近づいている。
成熟とは、文明が人間らしさを捨てる速度のことかもしれない。
本当の成熟とは、「理解の上でなお驚ける力」
老いない人とは、常に「再発見」できる人だ。
同じ景色を見ても、昨日と違う何かを感じ取れる人。
本当の成熟とは、理解した上でなお、驚ける力のこと。
それは理性と感受性のバランスであり、
“知っているけど、まだ感動できる”という矛盾の中に生まれる。
Z世代の静かな革命:「熱狂」から「静寂」へ
ただし、Z世代の“刺激を追わない”姿勢を
一概に退化と見るのは早計かもしれない。
彼らは「燃え尽きた社会」の中で、
新しい“静かな生”を模索している。
- 早く走る代わりに、立ち止まる
- 成功する代わりに、整える
- 語る代わりに、聴く
それは“熱狂の文明”から“静寂の文明”への移行かもしれない。
もはや「燃える」よりも、「澄ます」ことに価値がある時代が来ている。
結論:成熟と退化の狭間で
成熟と退化は表裏一体だ。
刺激を追わなくなった社会は老いる。
しかし同時に、刺激に支配された社会もまた、壊れていく。
だからこそ——
成熟とは、老いと再生の間にある「驚きの持続」だ。
私たちは、再び“驚ける自分”でいられるかどうかを、
日々、静かに問われている。