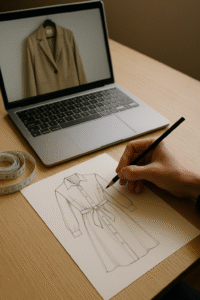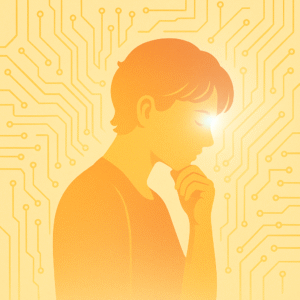日本の街を歩くと、興味深い光景が見えます。
外国人観光客はカメラを構え、顔を上げ、街の空気を楽しんでいる。
一方、日本人はほとんどがスマホを見つめ、イヤホンをつけ、
まるでこの街に「いながら、ここにいない」ように歩いている。
この違いは、単なる行動の癖ではありません。
それは、現代日本が抱える“感覚の断絶”の象徴です。
上を向く外国人、下を向く日本人
旅行者の脳は、未知の刺激を探す「探索モード」になっています。
だから、自然と視線は上がり、風景を味わおうとします。
一方、日常を生きる日本人の脳は、効率化のための「省エネモード」。
スマホの通知やタスクを処理することに最適化され、
外界への関心が閉じていくのです。
外国人は“世界を見に来ている”。
日本人は“世界の中で予定を消化している”。
イヤホンが生む「移動する個室」
ワイヤレスイヤホンは便利な道具ですが、
同時に「聴覚の壁」でもあります。
人はもともと、街の音から安全や人の気配を読み取ってきました。
しかしイヤホンをつけると、
私たちは“他人と同じ空間にいながら、存在しない人”になる。
イヤホンは、外界を拒絶する装置ではなく、
「誰にも触れられない私」を維持するための装置になった。
静寂を求めて耳を塞いだつもりが、
結果的に孤独を増幅する“無音の檻”に閉じこめられているのです。
本を読まない社会と「感じない脳」
読書とは、目で文字を追うことではなく、
言葉の背後にある“他人の世界”を想像する行為です。
しかし現代人は、短い動画や要約に慣れ、
思考の前段階をアルゴリズムに委ねるようになりました。
本を読むことは「時間の遅さ」を受け入れること。
でも、現代社会は“わからない時間”を耐えられなくなっている。
だから私たちは、本を閉じ、イヤホンをつけ、スマホの中へ逃げ込む。
読書離れとは、世界を感じる力の衰えでもある。
共通する根は「外界との断絶」
スマホも、イヤホンも、読書離れも、
根は同じです。
- 外界のノイズを避け、
- 他者の存在を煩わしく感じ、
- 自分だけの安全な世界に閉じこもる。
しかし、その「安全な世界」は、
本当は“感じない不自由”でできている。
聴かない自由が行き過ぎると、
感じない不自由になる。
もう一度「世界を感じる」ために
外を歩くとき、少しだけ顔を上げてみる。
イヤホンを外して、街の音を聞いてみる。
久しぶりに紙の本を開いてみる。
それだけで、
世界は驚くほど多層的に戻ってくる。
外の世界に何も感じなくなったのは、
世界が変わったからではない。
感じるための“沈黙の時間”を、
私たちが捨てたからだ。
結論
私たちは今、「情報の洪水」の中で、
世界を見失いかけている。
でも本当に失われたのは情報ではなく、
感じ取る力だ。
もう一度、耳を開き、目を上げ、
言葉を味わう時間を取り戻そう。
その瞬間、私たちは“生きた世界”と再びつながれる。