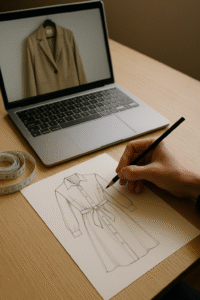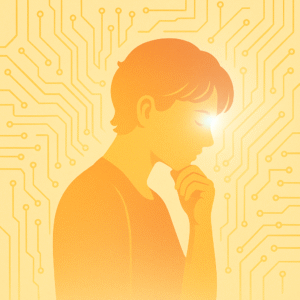はじめに
「心理的安全性」「多様性」「働きやすさ」など、人を尊重する組織文化が語られる時代になりました。
しかしその裏で静かに進行している問題があります。
それは、「責任を取らず、行動せず、リスクを取らない人間」が増えているという現実です。
彼らは「会社のため」「現場のため」と言葉にしながら、実際には動かない。
その“善意の代弁”こそが、組織の血流を止める原因になります。
1.「代弁者」という名の静かな病巣
「現場の声を代弁している」と自認する人はどの組織にもいます。
しかし多くは、他人の不満を言葉にするだけで、自らは行動しない。
そうした“行動なき代弁”は、結果として組織に次のような影響を与えます。
- 動く人ほど損をする文化が生まれる
- 行動よりも言葉が評価される
- 批評家が増え、挑戦が減る
代弁者の恐ろしさは、本人が善意で動いていることです。
彼らは「会社のため」と信じている。
しかしその正義感が、実は組織を蝕む“静かな癌”となっていくのです。
2.「心理的安全性」の誤用が組織を弱くする
心理的安全性とは、本来「安心して行動できる文化」を意味します。
しかし多くの現場ではこう誤解されています。
「何を言ってもいい」=「何もしなくてもいい」
発言だけが目的化し、責任や実行が伴わない。
それどころか、「批評が上手い人」が評価されるという歪みまで生まれます。
本来の心理的安全性とは、挑戦と行動のための安全性であり、
責任を回避する免罪符ではありません。
3.「行動なき正義」が最も危険である理由
代弁者が厄介なのは、自分を“正しい側”に置いていることです。
- 「自分は悪くない」
- 「仕組みが悪い」
- 「上が動かないから変わらない」
この言葉は一見論理的ですが、実際には責任を外に置く構造です。
本当に会社のためを思うなら、意見だけで終わらせず、
自ら一歩を踏み出す勇気が必要です。
4.これからの時代に必要なのは「成長責任」
これからの時代に必要なのは「指示待ち」でも「代弁」でもなく、
“自ら考え、動く責任”=成長責任です。
- 自分の意見に責任を持つこと
- 行動によって現実を変えること
- 失敗しても受け止め、次に活かすこと
この3つを放棄した瞬間、人は“代弁者”に堕ちます。
そして組織は、挑戦よりも弁明が上手な人間に支配されていきます。
5.リーダーの仕事は「動く人を守る」こと
経営者やリーダーが最も大切にすべきは、「声の大きい人」ではなく「行動する人」です。
- 批評より実践を評価する
- 挑戦の失敗を称賛する
- 行動する人を孤立させない
これを意識的に制度化しなければ、組織は声に引きずられます。
行動する人を守り抜くことこそ、リーダーの最大の責任です。
6.「優しさ」の誤用が企業を甘くする
日本社会は「調和」「優しさ」を大切にしてきました。
しかし、組織における優しさはときに“逃避”に変わります。
- 責任を取らせない優しさ
- 成果を曖昧にする優しさ
- リスクを避ける優しさ
それは、誰も育てない優しさです。
本当の優しさとは、行動と責任を通して人を成長させること。
経営とは、その厳しさを引き受ける覚悟です。
7.「代弁者」を重んじる経営者もまた、組織を蝕む
代弁者を生み出すのは、経営者自身の場合もあります。
「現場の声をよく伝えてくれる」
「社長の意見を理解してくれる」
「対立を避けてくれる」
そんな人物を右腕として重用し、
その言葉を鵜呑みにしてしまう経営者が少なくありません。
しかし、その“右腕”こそが、現場の真実を遮断する存在になっていることが多いのです。
8.「甘言」を見抜けないリーダーは現実を見失う
経営者は孤独です。
だからこそ、耳に心地よい言葉に弱くなる。
- 「社長の考えは正しいです」
- 「現場もだいたい納得しています」
- 「少し調整すれば大丈夫です」
この“安心させる報告”が続くと、経営者は仮想の現場を見始めます。
そして、本当の現場の痛みや摩擦からどんどん遠ざかっていく。
経営者が耳を塞ぐと、真実を言う人ほど離れ、
甘言を弄する人ほど残ります。
その先にあるのは、静かな崩壊です。
9.「右腕」とは、経営者自身の鏡である
本物の右腕とは、
- 耳の痛いことを言える人
- 失敗を恐れず現場に踏み込む人
- 利益より理念を優先して進言できる人
です。
「心地よい人」ばかりをそばに置けば、
経営者は現実から遠ざかります。
右腕の質は、経営者の成熟度の鏡です。
“誰を信じるか”ではなく、“どんな意見を聞ける自分であるか”。
そこに、経営者の器が現れます。
10.そして、それが不安であれば経営者自らが現場をやることです
現場を離れすぎた経営者ほど、情報の精度を失います。
もし不安があるなら、もう一度、自分の足で現場を見に行くことです。
現場の声を聞くのではなく、現場の空気を感じる。
人の顔、温度、違和感。そこにこそ経営の真実があります。
経営者が現場に戻ると、
“言葉の中にあった違和感”が“実態として見える”ようになります。
それが、代弁者に頼らない経営の第一歩です。
11.結論:組織を蝕むのは、悪意ではなく無責任
組織を壊すのは裏切りではなく、責任を取らない善意です。
行動しない代弁者、甘言を弄する側近、そしてそれを信じた経営者。
これらが揃ったとき、会社は静かに弱っていきます。
経営者が信じるべきは、あなたを安心させる人ではなく、
あなたに行動を促す人。
責任を取る人が組織を動かし、
行動する人が信頼を生み、
リスクを取る人が未来を拓く。
経営とは、行動する人の灯を絶やさないこと。
その覚悟がある限り、組織は必ず再生します。