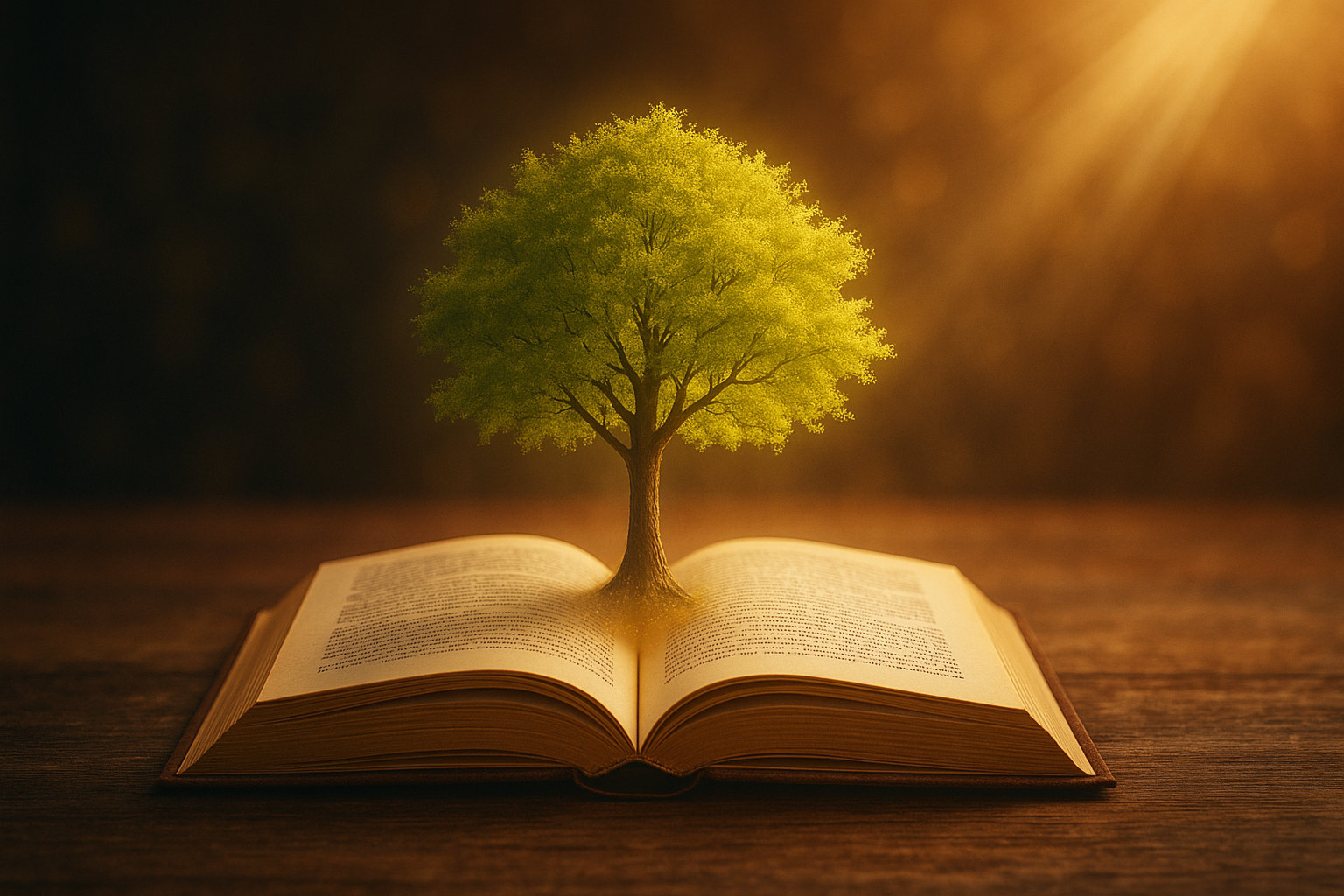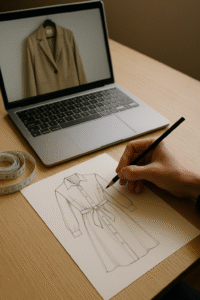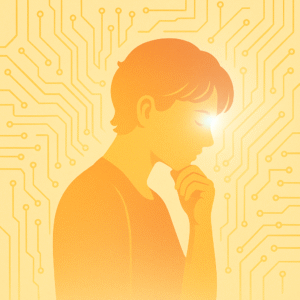「意味あるの?」と言われる資格でも、私にはちゃんと意味がある
「なんで今さらそんな資格を?」と言われても。私が今、資格を取る理由
「えっ?その資格、今の仕事に関係あるの?」「なんで今さらそんなことするの?」
そんなふうに言われること、実は結構あります。
でも、正直あんまり気にしていません。というか、むしろちょっと誇らしいくらいです。
なぜなら、私が資格を取るのは、“今”のためじゃなく、“これからの自分”のためだから。
目先の成果ではなく、未来の選択肢を広げるために、私は動いています。
選択肢は、多いほど人生は自由になる
私は常に「選択肢は多くあるべきだ」と思っています。
今は必要ないかもしれない。けれど、5年後、10年後の自分がどうなっているかなんて、誰にも分からない。
だからこそ、“やれる自分”を今から作っておく。
いざやりたいことが見つかったとき、「資格がないから無理だな…」じゃなくて、「よし、やってみよう」と動けるようにしておきたいんです。
そのために資格を取るというのは、私にとってごく自然な行動です。
目的があるから、取る資格を選んでいる
たとえば私は、不動産系の国家資格である「宅建士」と「賃貸不動産経営管理士」を持っています。
これは、将来的に不動産を複数所有して運用したいという思いがあるから。
さらに、宅建業としてのビジネス展開も視野に入れています。
ただし、「不動産四大資格」と呼ばれている他の2つ──「マンション管理士」と「管理業務主任者」には手を出していません。
理由は単純。私がビジネスをやろうとしている地域には、そもそもマンションがないから。
資格って、数を集めることが目的じゃない。
「自分がどう生きたいか」「どんな未来をつくりたいか」で選ぶものだと思っています。
やる気がなければ、資格は取れない
実際、資格って本気じゃないと取れません。
たとえば宅建士。知名度の高い資格ですが、合格率は決して高くありません。
とくに不動産業界で働いている人の合格率があまり高くないっていうのは、ちょっと意外かもしれませんが、これには理由があると思っています。
たぶん、会社に言われてなんとなく受ける人が多いから。
受験費用を会社が出してくれるし、昇進のために受けろと言われたから、とりあえず…という“記念受験”組も結構いる。
でもそれだと、本気になれない。やらされてる勉強って、やっぱり身にならないんですよね。
一方で、自分の意志で「将来こうしたいから必要なんだ」と目的意識を持って取り組んでいる人は、やっぱり強いです。
私自身も、自分の目標が明確だったからこそ、途中で投げ出さずに合格までたどり着けたと実感しています。
信頼を得るための“最低限の覚悟”としての資格
ちなみに、不動産屋さんで担当の方に話を聞くとき、その人が宅建士の資格を持っていないと、「この人、知識ちゃんとあるのかな…?」と正直ちょっと不安になります。
資格って、単なる肩書きじゃなくて、“最低限の覚悟”とか“信頼を得るための準備”でもあると思うんです。
資格はゴールじゃない。でも、確かなスタートにはなる
もう一つ、資格を取る利点は、その業界の基礎知識が身につくことです。
もちろん、資格を取ったからといって、すぐに現場で完璧に働けるわけじゃない。
実務になると、もっと深い知識や経験が必要になるのは当たり前です。
でも、地図なしで飛び込むよりも、ある程度の全体像を持って入れる方が、安心して学んでいける。
そういう意味でも、「ひとまずゴールに立つ」ことができる資格取得は、価値があると思います。
未来の自分が「やっておいてよかった」と思えるように
資格を取るのは、簡単なことではありません。
大人になってからの勉強って、仕事や家のこととも両立しなきゃいけないし、モチベーション維持も大変です。
でも、それでもやる理由がある。
「今の自分」ではなく、「未来の自分」に必要なことだから。
誰かに理解されなくても、笑われても、別にいい。
私はこれからも、自分の目標に向かって、必要だと思うことを一つずつ積み上げていくだけです。
おわりに
資格って、本当の意味では「勲章」じゃなくて、「可能性のチケット」みたいなものなんだと思います。
いつ使うかは自分次第。だけど、持っていなければ選べない道もある。
未来の自分のために、今日できる準備をしておく。
それが、私の資格との付き合い方です。
補足:知らなかったことを知る喜びも、立派な動機
そしてもうひとつ。
私は資格の勉強を通じて、「知らなかった世界を知ることって、こんなに楽しいんだ」と改めて感じることができました。
今まで知らなかった制度、業界の仕組み、法律の考え方…
勉強するたびに世界が広がっていく感覚があって、それが何よりの喜びです。
もし、「勉強って面白いかも」と思える人がいるなら、きっと資格取得に向いていると思います。
知ることを楽しめる人には、きっと未来も広がっていくと、私は信じています。